
三重県の偉人:本居宣長 — 「もののあはれ」を解き明かし、日本文化の核心に迫った知の巨人


三重県
「しきしまの やまとごころを 人とはば 朝日ににほう 山ざくら花」
この歌は、江戸時代の国学者であり医師であった本居宣長(もとおり のりなが)が、日本人の精神性を象徴する言葉として詠んだものです。
伊勢国松阪(現在の三重県松阪市)に生まれた彼は、生涯をかけて『古事記』を研究し、35年もの歳月をかけて注釈書『古事記伝』を完成させました。彼の学問は、中国由来の儒学や仏教に支配されていた当時の日本において、「もののあはれ」や「大和魂」といった日本固有の感性と精神性を探求する「国学」を大成させ、後の時代に大きな影響を与えました。
幼少期の読書好きから京都遊学へ
本居宣長は1730年(享保15年)、伊勢松坂の裕福な木綿仲買商、小津家の次男として生まれました。幼名は富之助。実家は江戸にも店を持つ豪商でしたが、彼は商売には興味を示さず、幼い頃から読書に熱中する少年でした。
11歳の時に父を亡くし、家業を継ぐことになりましたが、商才に恵まれなかったため、母の勧めもあり、23歳で医師を志して京都へ遊学します。京都での5年半に及ぶ遊学は、宣長の人生を決定づける重要な期間となりました。彼は儒学者の堀景山に儒学を、武川幸順(たけかわ こうじゅん)に医学を学ぶ傍ら、平安文学や古典に触れ、特に契沖(けいちゅう)の著作に感銘を受けました。契沖が用いた文献考証学という実証的な研究手法は、後の宣長の学問の基礎となりました。
師・賀茂真淵との「松阪の一夜」と『古事記伝』
宝暦7年(1757年)、松坂に帰郷した宣長は、医者を開業する傍ら、自宅で『源氏物語』の講釈を始め、古典研究に本格的に取り組みます。この頃、賀茂真淵(かもの まぶち)の『冠辞考(かんじこう)』を読み、古代語に秘められた日本固有の精神性に強く惹かれ、真淵に手紙で入門を志願します。
しかし、真淵が多忙であったため、直接の指導は叶いませんでした。ところが、宝暦13年(1763年)5月、伊勢神宮参宮のために松阪を訪れた真淵と、一夜限りで対面する機会を得ます。これが有名な「松阪の一夜」です。この出会いで、宣長は真淵から『古事記』の研究を勧められ、生涯をかけて取り組むべき課題を定めます。
宣長は、この真淵との出会いを機に、『古事記』の本格的な研究に着手しました。当時、その独特な文体からほとんど読まれなくなっていた『古事記』を、宣長は一字一句丁寧に読み解き、古語や仮名遣いの考証に没頭しました。昼間は医師として働き、夜は書斎にこもるという、40年以上にわたる二重生活を送り、ついに69歳になった1798年(寛政10年)、全44巻に及ぶ大著『古事記伝(こじきでん)』を完成させました。
宣長の思想:和歌と「もののあはれ」
本居宣長の思想は、彼が医師として、また国学者として、現実と学問の両方から培ったものであり、特に「もののあはれ」と「大和魂」という二つのキーワードに集約されています。
『源氏物語』に見出した「もののあはれ」
宣長は、和歌や古典文学、特に『源氏物語』の研究を通じて、「もののあはれ」という日本固有の情緒こそが文化の本質であると考えました。「もののあはれ」とは、物事に触れたときに自然と湧き上がる感情の動きであり、それは嬉しさや悲しみ、哀愁といった繊細な心の揺れを素直に受け入れる感性です。
彼は、儒教の「善悪」や「理屈」といった中国由来の思想(「漢意(からごころ)」)が、日本人の素直な心(「大和心(やまとごころ)」)を抑圧していると批判し、感情を尊重する「もののあはれ」こそが、日本文化の真髄であると主張しました。この思想は、単なる文学理論に留まらず、後の思想家や文化人にも大きな影響を与えました。
権力に迎合しない姿勢と「鈴屋」
宣長は、その名声から紀州藩主に仕官を求められますが、「一般患者の診療ができなくなる」という理由で再三これを断りました。しかし、藩主が彼の願いを認め、特例として自宅での診療を続けることを許したため、五人扶持(ごにんぶち)という形で仕官しました。彼のこの姿勢は、学問や医療を権力のために使うことを潔しとしない、彼の誠実さを物語っています。
また、宣長は鈴をこよなく愛し、自宅の書斎を「鈴屋(すずのや)」と名付け、多くの鈴を蒐集しました。鈴は、彼の学者としての象徴となり、松阪市のシンボルとしても市民に愛されています。
宣長の遺産
本居宣長の学問は、単なる古典研究ではありませんでした。彼は、上代語や文法、地名の考証など、言語学的な手法を駆使して、日本人のものの考え方や文化の成り立ちを解き明かそうとしました。その研究成果は、現代の日本語学や国語教育の礎となっています。
彼の思想は、幕末の尊王攘夷運動にも影響を与え、明治維新の精神的基盤の一つとなりました。しかし、宣長自身は現実の政治を動かすことには否定的で、あくまで在野の学者として、理想的な「古道」を説くことに徹しました。
彼の「生涯にわたる学び」への姿勢は、71歳で亡くなる直前まで患者を診察し、研究を続けていたことからもうかがえます。そして、彼の膨大な日記や著述は、当時の庶民の生活や風俗、社会の様子を伝える貴重な歴史史料となっています。
宣長の生涯は、私たちに、豪奢や名声ではなく、日々の暮らしを大切にし、自らの心に誠実に向き合うことこそが、人生を豊かにする道であることを教えてくれます。彼の遺した思想と精神は、現代に生きる私たちに、改めて「日本人とは何か」を問いかけ、自分たちの文化とアイデンティティを見つめ直す勇気を与え続けているのです。
本居宣長ゆかりの地:国学の足跡を辿る旅
本居宣長の足跡は、彼の生まれ故郷である三重県松阪市を中心に、彼が学問の道に入った京都、そして彼を慕う門人たちの拠点へと繋がっています。
- 本居宣長記念館(三重県松阪市殿町):宣長の旧宅「鈴屋」に隣接し、彼の自筆稿本や遺愛の品々を多数所蔵・展示しています。
- 本居宣長旧宅(鈴屋)(三重県松阪市殿町):宣長が12歳から72歳まで暮らし、『古事記伝』を執筆した書斎「鈴屋」がある家です。国の特別史跡に指定されています。
- 本居宣長ノ宮(三重県松阪市殿町):宣長を祭神として祀る神社です。
- 樹敬寺(じゅきょうじ)(三重県松阪市):本居家の一族の菩提寺であり、宣長夫妻と長男・春庭の墓があります。
- 本居宣長先生修学之地碑(京都市下京区):宣長が京都で儒学の師・堀景山に学んだ場所を示す石碑が建っています。
- 新上屋(しんじょうや)跡(三重県松阪市魚町):宣長が師・賀茂真淵と最初で最後の対面を果たした場所です。
- 本居宣長墓所(三重県松阪市山室町妙楽寺):宣長が「好んだ」という山室山の奥墓に眠っています。
本居宣長の遺産:現代社会へのメッセージ
本居宣長の生涯は、私たちに「自己のルーツを深く探求すること」の重要性を教えてくれます。彼は、西洋の学問や文化が流入する現代において、自分たちの足元にある文化や言葉にこそ、真の価値があることを発見しました。
彼の「もののあはれ」の思想は、感情や情緒を尊重する日本人の気質を再認識させ、現代の教育や社会においても、理屈だけではない「感じる力」の大切さを示唆しています。宣長の遺した膨大な著作と精神は、私たちが自らのアイデンティティを見つめ直し、豊かな未来を創造するための羅針盤となるでしょう。
(C)【歴史キング】
関連する書籍のご紹介

本居宣長 (中公新書) / 田中 康二 (著)
新書 – 2014/7/24
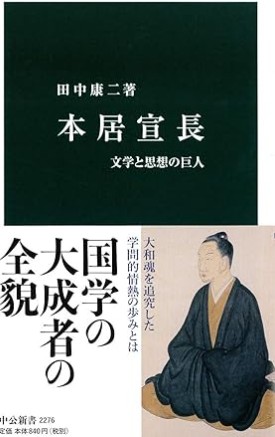
『古事記伝』で知られる国学者・本居宣長。その七十年の生涯を辿りつつ、文学と思想の両分野に屹立する学問的偉業の全体像を描き出す。

本居宣長「うひ山ぶみ」 (講談社学術文庫 1943) / 白石 良夫(全訳注) (著)
文庫 – 2009/4/13
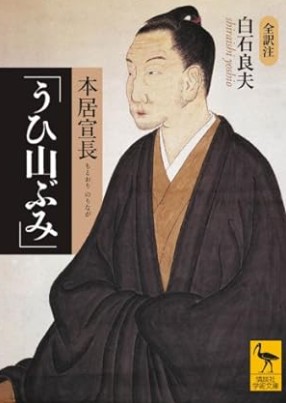
国学の大偉人が弟子に教えた学問の要諦とは 「からごころ」を排して「やまとたましい」を堅持することで、真実の「いにしえの道」へと至ることが学問の道である。契沖に始まる国学の目的と方法を説く入門書






