
長崎県の偉人:西川如見 — 将軍吉宗が下問し、町人の道を説いた知の巨人
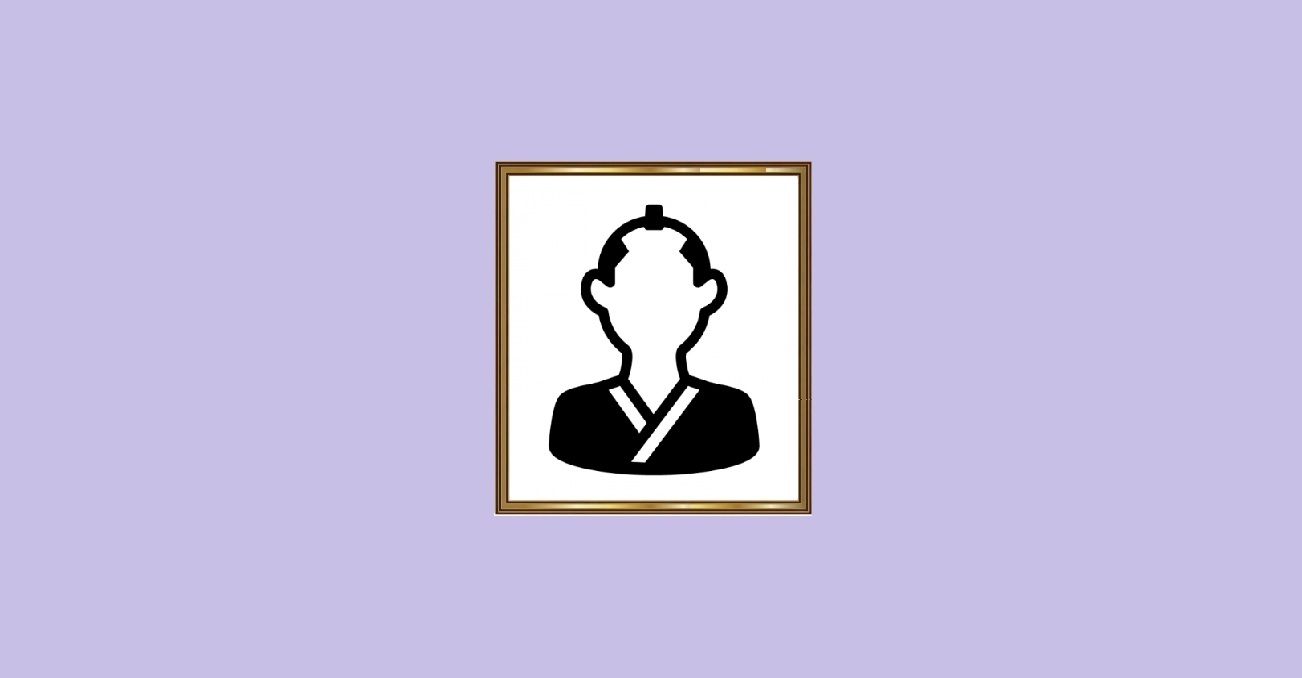

長崎県
「町人嚢(ちょうにんぶくろ)」や「百姓嚢(ひゃくしょうぶくろ)」
という書物を、あなたはご存じでしょうか。
これらは、江戸時代中期に長崎の町人として、日本最高の天文学者・地理学者と称えられた西川如見(にしかわ じょけん)が、町人や農民のために書いた教訓書です。鎖国という時代にあって、彼は長崎から得られる海外情報をもとに、日本で最初の本格的な世界地理書『華夷通商考』を著しました。彼の学問は、町人でありながら八代将軍徳川吉宗が意見を求めるほどのものであり、その著作に込められた本質的な平等思想と合理的な思考は、時代を遥かに先駆けていました。
幼少期の苦難から学問の道へ
西川如見は、1648年(慶安元年)、肥前長崎の商家に生まれました。幼い頃に父を亡くし、女手ひとつで育てられるという苦労を経験します。しかし、彼は勉学への情熱を失うことはありませんでした。25歳の頃、儒学者の南部草寿(なんぶ そうじゅ)に和漢学を学び、さらに林吉左衛門の流れをくむ小林義信(こばやし よしのぶ)から天文学、暦学、測量学といった南蛮系の学問を学びました。
当時の長崎は、海外との唯一の窓口として、中国やオランダから新しい知識や情報が怒涛のように流れ込んでくる街でした。如見は、この特殊な環境を最大限に活かし、和漢洋のあらゆる学問を貪欲に吸収しました。彼は、自らの学問を「天学」(自然摂理と人間社会を対象とした学問)と名付け、その探求に生涯を捧げました。
鎖国日本の「窓」となった世界地理書
1695年(元禄8年)、48歳になった如見は、長崎での見聞をもとに、日本で初めての世界地誌『華夷通商考(かいつうしょうこう)』を著しました。この書物には、中国、朝鮮、琉球、台湾、東南アジア、南アジア、そして西洋諸国との通商関係や地理が詳細に記述されていました。さらに1708年(宝永5年)には、『増補華夷通商考』を刊行。この書物では、日本で初めて南北アメリカ大陸が紹介されるなど、鎖国下にあった日本の人々にとって、未知の世界を知るための貴重な情報源となりました。如見の天文学の知識は、当時の日本の学者たちの中でも傑出していました。地球が球形であるという説を早い段階で唱え、中国の天文学説を主としながらも、西洋天文学の特徴を十分承知していました。彼の天文学や地理学に関する著述は、『両儀集説』『日本水土考』など、多数にわたります。
将軍吉宗との出会いと「町人道」の提唱
如見の学識は、当時の江戸幕府にも知られるようになります。1719年(享保4年)、8代将軍徳川吉宗は、彼を江戸に招き、天文学に関する意見を求めました。これは、一介の町人である如見が、将軍から「下問」(身分の高い者が低い者に質問すること)を受けるという、異例中の異例の出来事でした。彼は、学問を通じて得た知見を、一般の庶民にも役立てたいという強い思いを持っていました。町人や農民の生活の心得を説いた教訓書『町人嚢』と『百姓嚢』は、その代表的な著作です。
- 本質的な平等思想: 『町人嚢』の中で、如見は、中国の身分制度を日本に当てはめながらも、「畢竟(ひっきょう)人間は根本の所に尊卑有るべき理なし」(結局人間は、根本のところに尊い賤しいがあるわけではない)と説き、四民の本質的な平等を力強く主張しました。
- 町人の心得: 町人が謙下(謙虚)で質素な生活を送ること、他人の威勢を羨まず、自分の分限に安んじることが、一生の楽しみを尽くす道であると説きました。
- 百姓の心得: 『百姓嚢』では、農民が驕慢の心を持たず、正直に農業に励むことの大切さを説くとともに、公の御制札(ごせいさつ)を読み解き、道理をわきまえることの重要性を説きました。
これらの著作は、単なる道徳の書ではなく、当時の庶民の社会意識や経済状況を理解するための貴重な歴史資料となっています。
熊沢蕃山との「水土論争」と批判的合理主義
如見の思想は、同時代の儒学者たちとの間で、様々な議論を巻き起こしました。特に、岡山藩の儒学者である熊沢蕃山(くまざわ ばんざん)との「水土(すいど)論争」は有名です。蕃山は、日本・中国・インドでは「水土」(土地や地理環境)が異なるため、儒教、仏教、神道といった三つの教えは、それぞれの風土にしか適合しないと説きました。これに対し、長崎に居住し、最新の海外情報を得ていた如見は、『水土解弁』を著して蕃山の説を批判。当時の中国では火葬が行われていないという事実を突きつけ、蕃山の議論の矛盾を指摘しました。この論争は、近世日本の思想史において、事実と論理を重視する「合理主義」の先駆けとして位置づけられています。如見は、人智を超えたものへの「畏敬の念」は必要だとしながらも、根拠のない迷信や空論を徹底的に排斥しました。
西川如見ゆかりの地:知の足跡を辿る旅
西川如見の足跡は、彼の故郷である長崎市を中心に、彼を育てた土地に今も残されています。
- 西川家跡の説明板(長崎市桶屋町6):如見の生家跡を示す説明板が、麹屋町の郵便局前に建っています。
- 西川如見墓所(長崎市寺町・長照寺後山墓地):如見の遺骨が眠る墓所です。
西川如見の遺産:現代社会へのメッセージ
西川如見の生涯は、私たちに「情報と知識を求める探究心」の重要性を教えてくれます。彼は、鎖国という厳しい時代にあっても、長崎という限られた窓から、貪欲に世界の知識を吸収し、それを日本の人々にわかりやすい形で伝えました。彼の著作に込められた本質的な平等思想と合理的な思考は、身分制度が厳然として存在した江戸時代にあって、まさに時代を先駆けるものでした。彼は、町人や百姓といった庶民にも学問の道を開き、人々の意識を変えることこそが、国の真の繁栄につながると信じていました。西川如見の物語は、一人の町人が、その知性と情熱によって、閉ざされた時代を切り開き、人々の心に希望を与えることができることを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、知識を求め、それを社会に活かすことの大切さを、力強く語りかけているのです。






