
岡山県の偉人:緒方洪庵 — 幕末の蘭学医が築いた「日本近代医学の礎」
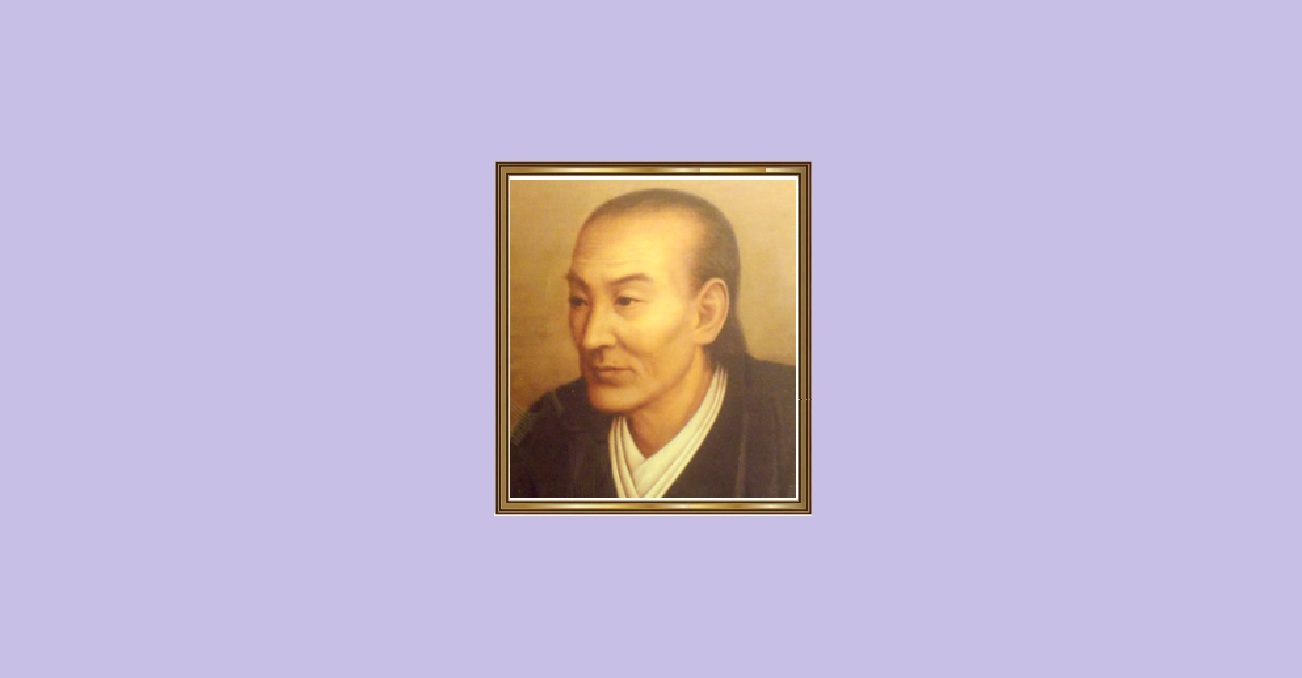
プロフィール
緒方 洪庵(おがた こうあん)
1810(文化7)年8月13日生│1863(文久3)年7月25日没(52歳)
「適塾(大阪大学の前身)」「日本の近代医学の祖」
「医の世に生活するは人の為のみ、おのれが為にあらず」
この言葉は、江戸時代末期に大阪で蘭学塾「適塾」を開き、多くの俊英を育てた緒方洪庵(おがた こうあん)が、医師としての自らの信条を門弟たちに説いたものです。備中国足守藩(現在の岡山県岡山市)の武士の家に生まれた彼は、生涯をかけて西洋医学の普及に努め、当時不治の病とされた天然痘の予防、コレラの治療に尽力しました。福澤諭吉、大村益次郎、佐野常民など、後の日本を動かした偉人たちが彼のもとで学び、その教えは日本の近代化を力強く後押ししました。
幼少期の学びと医学の道への志
緒方洪庵、幼名・騂之助(せいのすけ)は、1810年(文化7年)、備中足守藩士の三男として生まれました。幼い頃に天然痘を患った経験から、彼は医学への関心を深めていきました。16歳で元服を済ませると、父と共に大坂へ出て、蘭方医・中天游(なか てんゆう)の私塾「思々斎塾」に入門。4年間にわたり、蘭学と西洋医学の基礎を徹底的に学びました。彼の学問への情熱は、師の天游も舌を巻くほどでした。塾の蔵書を片っ端から読み漁り、わずか3年で全ての書物を読み終えたといいます。師の勧めで江戸へ出た洪庵は、坪井信道(つぼい しんどう)、宇田川玄真(うだがわ げんしん)のもとでさらに研鑽を積み、長崎ではオランダ人医師ニーマンに学び、蘭方医としての腕を磨きました。
適塾の開塾と感染症との闘い
30歳になった1838年(天保9年)、洪庵は大阪に戻り、瓦町で医業を開業。同時に蘭学塾「適塾(てきじゅく)」を開きました。この適塾は、身分や階級にとらわれず、向学心に燃える若者たちを広く受け入れました。洪庵は、福澤諭吉に「先生の微笑んだ時のほうが怖い」と言わしめるほど、厳格な態度で教育にあたりました。しかし、その厳しさの裏には、生徒たちの成長を願う温かい心がありました。腸チフスを患った福澤諭吉を手厚く看病したり、学問を諦めかけていた生徒を励ましたりと、洪庵は生涯にわたり、生徒たちを我が子のように愛しました。この頃、洪庵が特に力を注いだのが、感染症との闘いでした。
- 天然痘の予防: 1849年(嘉永2年)、洪庵は大阪に「除痘館(じょとうかん)」を設立。無料で牛痘種痘法(ワクチン)を広め、全国186箇所に分苗所を設けるなど、天然痘の予防に尽力しました。これにより、天然痘の患者数は劇的に減少し、後の予防医学の礎となりました。
- コレラとの闘い: 1858年(安政5年)、コレラが日本で大流行し、「コロリ」と呼ばれて人々を恐怖に陥れました。緒方洪庵は、蘭学書を読み漁り、わずか1週間でコレラの治療手引き書『虎狼痢治準(ころうりちじゅん)』を執筆。医師たちに無料で配布し、多くの命を救いました。
幕府への出仕と悲劇的な最期
洪庵の功績は、幕府にも認められ、1862年(文久2年)、彼は幕府の度重なる要請により、奥医師兼西洋医学所頭取として江戸に出仕します。しかし、堅苦しい宮仕えの生活は、自由を愛する洪庵には合わず、心身を蝕んでいきました。そして、文久3年(1863年)、江戸の役宅で突然喀血し、54歳でこの世を去りました。洪庵の死後も、彼の遺志は受け継がれました。適塾は、大阪大学のルーツとなり、洪庵の著した病理学書『病学通論』は、日本医学の近代化に大きな影響を与えました。
📍緒方洪庵ゆかりの地:蘭学の足跡を辿る旅
緒方洪庵の足跡は、彼の故郷である岡山県から、蘭学と医学を学んだ大阪、そして最期の地である東京へと繋がっています。
- 緒方洪庵誕生地(岡山県岡山市北区足守):彼の生誕地であり、宅地と古井戸が残されています。
- 適塾(大阪市中央区北浜3-3-8):洪庵が開いた蘭学塾で、国指定重要文化財となっています。
- 除痘館跡(大阪市中央区道修町):洪庵が種痘を始めた場所です。美々卯本店別館の入り口には、古手町除痘館跡の碑が残る。
- 除痘館記念資料室(大阪市中央区今橋3-2-17 緒形ビル4F):「除痘館」の活動と足跡を記念して、資料の展示、公開している。
- 緒方洪庵墓所(大阪市北区同心1-3-1 龍海寺):恩師・中天游(なかてんゆう)を慕って同じ龍海寺に自らの墓(遺髪)を建てた。洪庵の墓の傍に弟子・大村益次郎の切断した右足が葬られている。これは益次郎が洪庵を慕った遺言によるもの。
- 緒方洪庵墓所(東京都文京区向丘2-37-5 高林寺):江戸でのもう一つの墓所(遺骨)です。
💬緒方洪庵の遺産:現代社会へのメッセージ
緒方洪庵の生涯は、私たちに「学び続けることの重要性」を教えてくれます。彼は、生涯を通じて蘭学を学び続け、その知識を、種痘の普及やコレラの治療法といった、人々の命を救う「実学」へと昇華させました。彼の「適塾精神」は、単なる医学の知識を伝えるだけでなく、人としてどう生きるべきかという「医の倫理」を説いたものです。これは、現代の医療現場で働く私たちに、医療の本質が、単なる技術ではなく、患者への深い共感と奉仕の心にあることを、力強く教えてくれます。緒方洪庵の物語は、一人の医師が、その情熱と知性によって、感染症という時代を超えた脅威に立ち向かい、多くの人々の命を救うことができることを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、社会貢献という真の豊かさを追求する智慧を、力強く語りかけているのです。
©【歴史キング】






