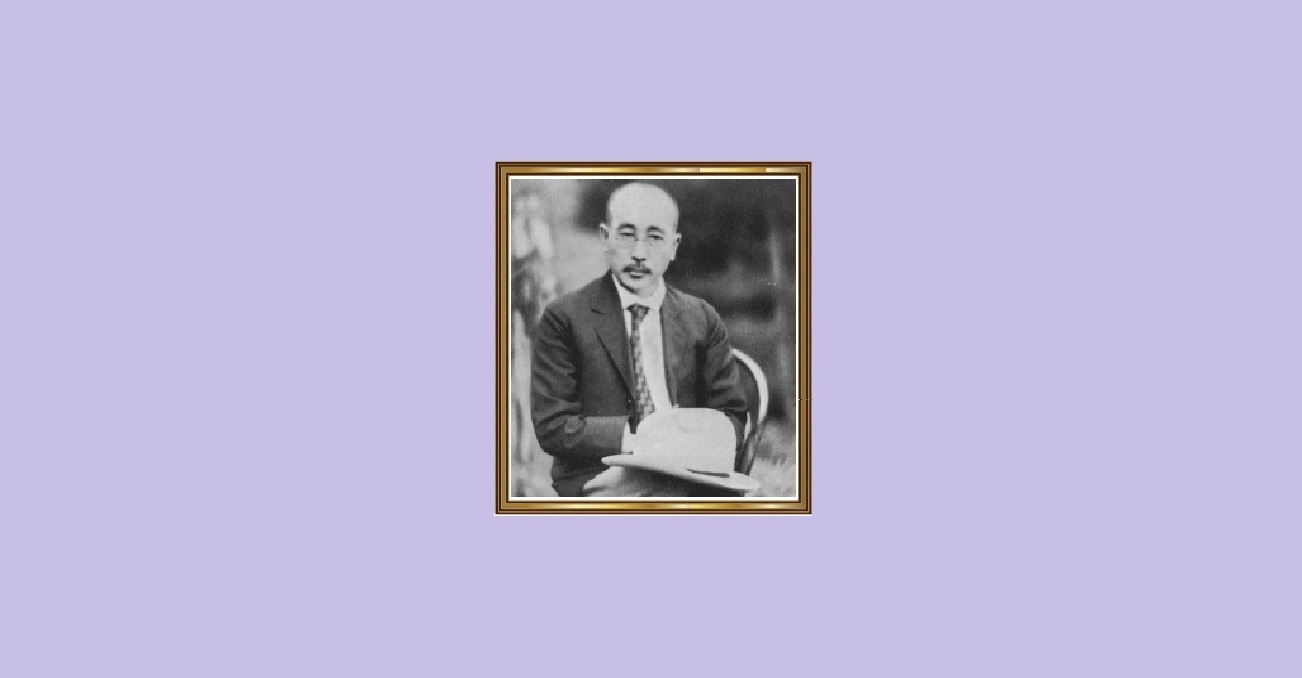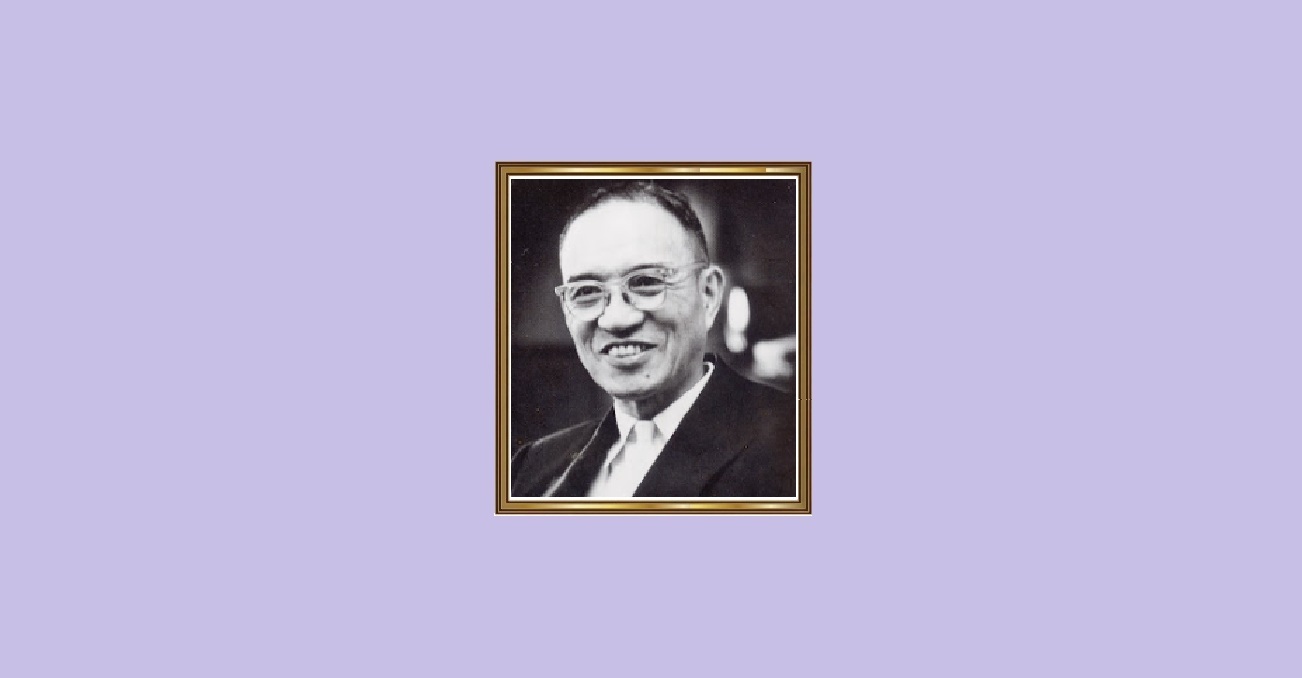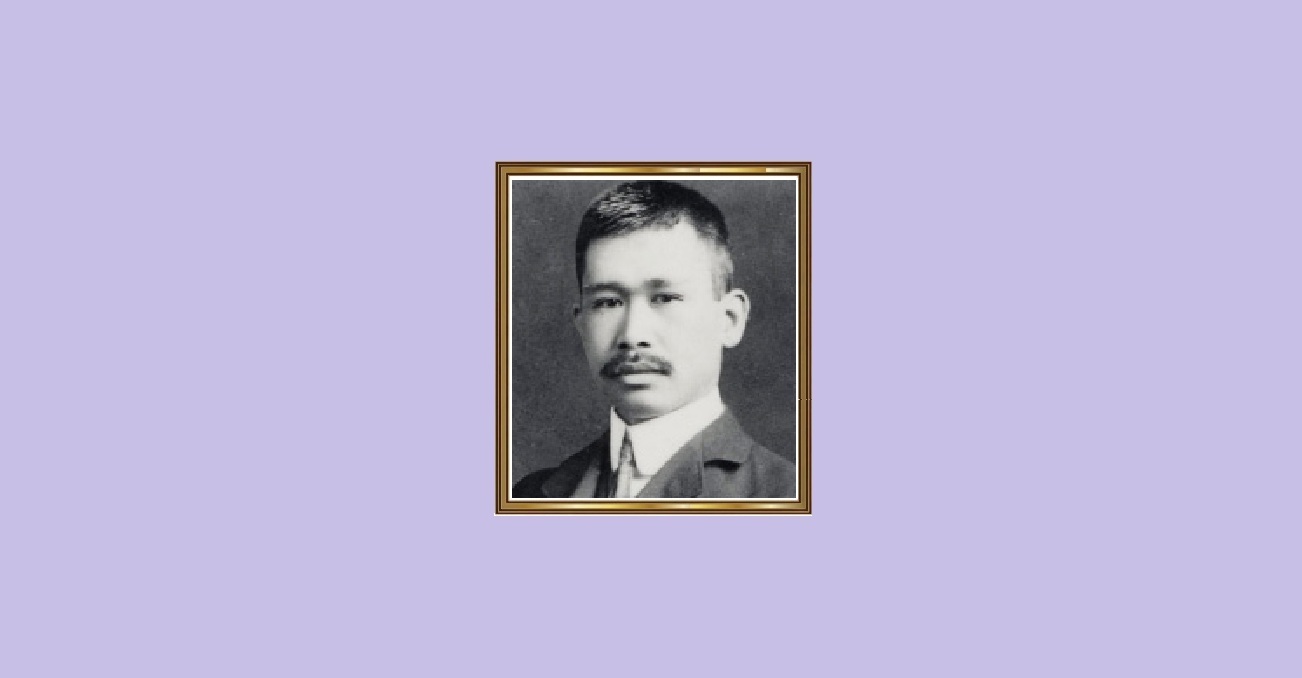神奈川県の偉人:尾崎行雄 — 「憲政の神様」「議会政治の父」が描いた民主主義の軌跡
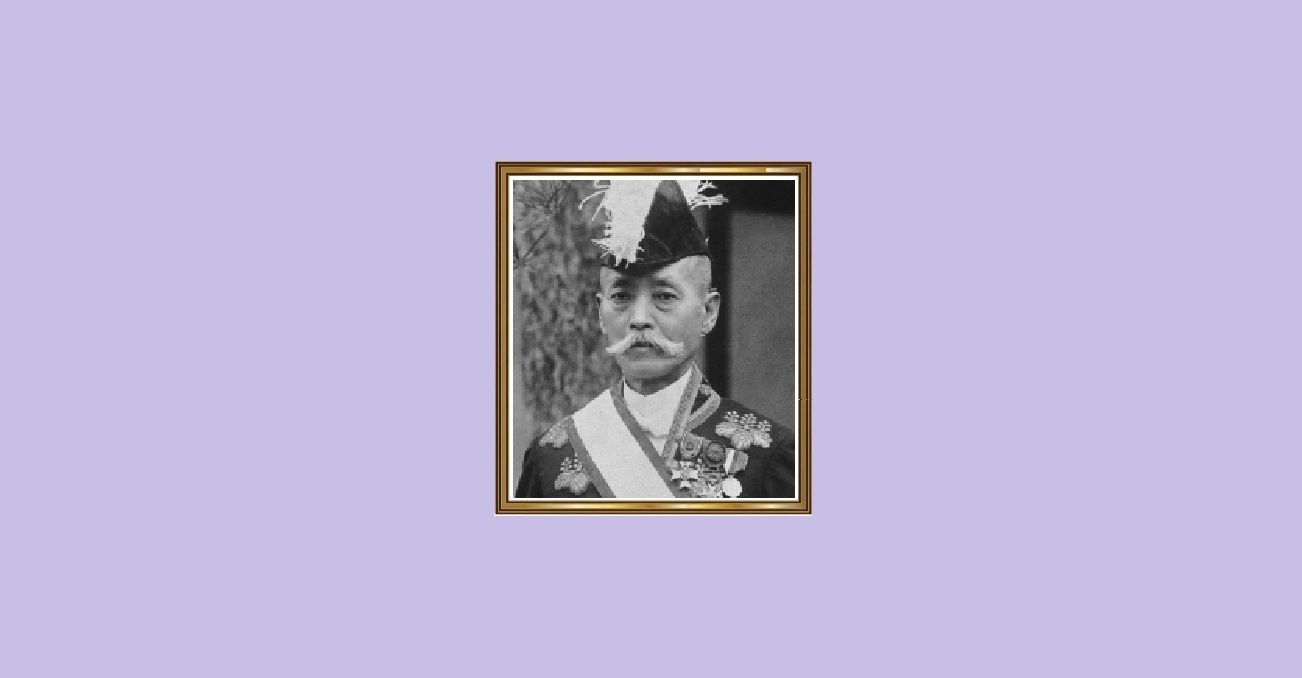
プロフィール
尾崎 行雄(おざき ゆきお)
1858(安政5)年12月24日生│1954(昭和29)年10月6日没(95歳)
「憲政の神様」「議会政治の父」
「人生の本舞台は常に将来に在り」
この言葉は、明治・大正・昭和の三代にわたり、実に63年間にわたって衆議院議員を務め続けた尾崎行雄(おざき ゆきお)が残した、揺るぎない人生観を表しています。相模国(現在の神奈川県相模原市)に生まれた彼は、当選回数25回、衆議院名誉議員第1号という、世界議会史上稀に見る記録を打ち立てました。真の民主政治と世界平和の実現を目指し、あらゆる権力の弾圧に屈せず、常に民衆の側に立って闘い続けた彼の生涯は、日本の民主主義の歴史そのものです。
幼少期の感化と、若き日の苦闘
尾崎行雄、幼名・彦太郎は、1858年(安政5年)、相模国津久井郡又野村(現在の神奈川県相模原市)に生まれました。父・尾崎行正は、漢方医を家業とし、儒学者・藤森弘庵のもとで学んだ人物です。行雄は11歳まで故郷で過ごした後、父の転任に伴い、三重県伊勢市へと移住します。慶應義塾に入学した尾崎は、塾長福澤諭吉にその才能を認められ、最下級から最上級生へと駆け上がります。ここで彼は、キリスト教の洗礼を受け、後の彼の人生哲学の根幹を築きました。しかし、工学寮(後の東京大学)への転学を巡って福澤と対立し、慶應義塾を退学。その後、工学寮に入学するも、学風の違いから再び退学し、『曙新聞』などに薩摩藩閥の横暴を批判する投書を始めるなど、ジャーナリストとしての頭角を現します。
「共和演説事件」と政治家としての覚悟
明治23年(1890年)、第1回衆議院議員総選挙で三重県選挙区から出馬し、初当選を果たします。この当選が、63年におよぶ彼の議員生活のスタートとなりました。尾崎は、大隈重信内閣の文部大臣に就任した際、帝国教育会での演説で、天皇制を否定するものではないにもかかわらず、言葉尻をとらえられ「共和演説事件」として攻撃を受けます。彼はこの事件で文部大臣を辞任し、憲政党も総辞職に追い込まれました。この経験は、彼の政治家としての覚悟を一層強固なものにしました。
伏魔殿・東京市政との闘いと「桜の寄贈」
明治36年(1903年)、尾崎は政界の要請を受け、東京市長に就任します。当時の東京市政は、贈収賄事件が横行し、「伏魔殿」と呼ばれるほど腐敗していました。
9年間の市政改革
尾崎は、9年におよぶ在任期間中、東京市政の近代化に尽力しました。
- インフラ整備: 上水道拡張、下水道工事、道路改良、街路樹の植栽などを積極的に推進しました。特に、悪路と砂塵に苦しむ市民のため、政府の支援を待たずに道路改良に取り組みました。
- 東京市電の市有化: 市民の不利益となっていた民営の電車事業を、政府の抵抗を受けながらも強引に買収し、東京市電気局を設置。これにより、東京の交通インフラは安定し、市民の利便性が向上しました。
- 多摩川水源林の確保: 長期的な視点から水源林の滋養に着手し、多摩川流域の山林を買い上げ、東京の安定した水源を確保しました。
ワシントンD.C.への桜の寄贈
尾崎の東京市長時代の特筆すべき功績の一つが、日米親善の象徴となったワシントンD.C.への桜の寄贈です。日露戦争後の緊張緩和を目指していた尾崎は、タフト大統領夫人の発案を知り、東京市からソメイヨシノの苗木をワシントンへ贈呈することを決意します。一度目の苗木は害虫で焼却されてしまうという悲劇に見舞われますが、尾崎は諦めず、再度健康な苗木を育成させ、3,000本を寄贈しました。この桜は、現在もポトマック河畔を彩り、「全米桜祭り」として日米親善のシンボルとなっています。
桂太郎弾劾演説と軍国主義との闘い
東京市長を辞任し、国会に戻った尾崎は、日本の議会政治を守るための闘いの中心となっていきます。
「玉座を胸壁とするもの」への糾弾
大正元年(1912年)、軍閥の意向で内大臣の桂太郎が首相に就任すると、尾崎はこれを「宮中・府中の別を乱すもの」と厳しく批判。国会での弾劾演説で、桂首相を「玉座を胸壁とし詔勅を弾丸とするもの」と糾弾し、これが大正政変の引き金となりました。この雄弁と信念が、尾崎を「憲政の神様」と呼ばしめる所以です。
非戦論と普通選挙運動
第一次世界大戦後の欧米視察で戦争の悲惨さを知った尾崎は、一貫した平和主義者へと転じます。
- 軍縮運動: 巨額の軍事費に苦しむ国の財政を憂い、議会で軍縮を強く主張。全国遊説を行い、軍縮の世論を喚起しました。
- 普通選挙の推進: ポピュリズムを危惧していたものの、大正デモクラシーの進展とともに、普通選挙運動の先頭に立ち、婦人参政権も支持するなど、民主主義の普及に尽力しました。
- 反軍国主義: 治安維持法反対運動や、軍部を批判する演説を続け、翼賛選挙にも非推薦で出馬。昭和18年(1943年)には、川柳の引用がもとで「不敬罪」に問われるなど、命がけで軍国化に抵抗しました。
永遠の議員と、現代への遺産
尾崎は、戦後の総選挙でも三重県からトップ当選を果たし、民主主義の復活に尽力。落選するまでの63年間、議会政治の現場に立ち続けました。彼の座右の銘「人生の本舞台は常に将来に在り」の通り、彼は常に前向きな姿勢を崩さず、94歳まで衆議院議員を務めました。
📍尾崎行雄ゆかりの地:民主主義の足跡を辿る旅
尾崎行雄の足跡は、彼の故郷である神奈川県相模原市から、市政を担った東京、そして晩年の逗子へと繋がっています。
- 尾崎咢堂記念館・生家(神奈川県相模原市緑区又野691):彼が11歳まで過ごした生家跡と、彼の功績を伝える記念館があります。写真や肖像画、遺品のほかに幅広い活動の足跡を物語る資料が保存、展示されています。
- 尾崎咢堂記念館(三重県伊勢市川端町97-2):昭和34年4月16日、神都の清流宮川河畔の咢堂精神発祥の地とも言うべき旧尾崎邸宅に陳列室、ロビー、結婚式場の施設を添え、落成開館した。平成14年9月、施設の老朽化により全面改築に着手し、展示室を充実させた記念館として平成15年11月15日に新装開館となった。
- 尾崎行雄記念碑(神奈川県逗子市新宿5-4-1・披露山公園):彼が晩年を過ごした逗子の街を見下ろす公園に建っています。
- 憲政記念館(東京都千代田区永田町1−1−1):尾崎の功績を称えて建設された施設であり、前庭に銅像があります。
- 尾崎行雄墓所(円覚寺黄梅院・神奈川県鎌倉市山ノ内)
💬尾崎行雄の遺産:現代社会へのメッセージ
尾崎行雄の生涯は、私たちに「信念を貫く政治の力」を教えてくれます。彼は、権力や利権に屈することなく、国民の権利と平和を最優先する政治姿勢を貫きました。彼の「投票の心得」に込められた、国民一人ひとりが政治的意欲を持ち、自らの意思を明確にすることの大切さは、現代の民主主義社会においても、最も重要な教訓です。尾崎行雄の物語は、一人の政治家が、その雄弁と信念によって、時代の暗雲に立ち向かい、民主主義という光を灯し続けたことを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、政治への関心と、理想を追い求める勇気を持つことの大切さを、力強く語りかけているのです。