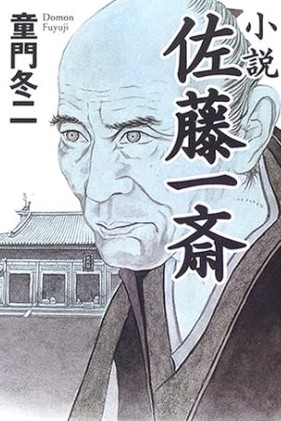岐阜県の偉人:佐藤一斎 — 3000人の俊英を育て、幕末維新を導いた「言志四録」の師


岐阜県
「少(しょう)にして学べば、則(すなわ)ち壮(そう)にして為(な)すことあり。壮にして学べば、則ち老いて衰(おとろ)えず。老いて学べば、則ち死して朽(く)ちず」
この「三学戒」と呼ばれる言葉は、幕末から明治維新にかけて、日本の行く末を担う多くの指導者たちに影響を与えた儒学者、佐藤一斎(さとう いっさい)が遺したものです。
美濃国岩村藩の家老の子として江戸に生まれた彼は、幕府の最高学府である昌平黌(しょうへいこう)の総長を務め、3000人もの門下生を育てました。その思想は、西郷隆盛の座右の書『言志四録』として、激動の時代を駆け抜けた志士たちの心の支えとなりました。
幼少期の才覚と学問の道への志
佐藤一斎は1772年(安永元年)、岩村藩の家老・佐藤信由の次男として、江戸の岩村藩邸下屋敷に生まれました。幼い頃から読書を好み、水練、射騎、刀槍といった武芸にも秀でるなど、文武両道に才能を発揮しました。18歳の時に岩村藩に仕え、藩主の側近として仕えますが、翌年に職を辞して大坂へ遊学します。儒学者の皆川淇園(みながわ きえん)や中井竹山(なかい ちくざん)に学び、その後、江戸に戻り、幕府の儒官・林家の門下となりました。彼の人生の大きな転機は、34歳で林家の塾長に就任したことです。彼は、大学頭(だいがくのかみ)・林述斎(はやし じゅっさい)と共に、多くの若者たちの指導にあたり、その類まれな指導力と学識の深さから、官学の頂点である昌平黌(しょうへいこう)の総長にまで上り詰めました。
「陽朱陰王」の思想と3000人の門下生
一斎の学問は、表向きは幕府の官学である朱子学を専門としていましたが、内心では「知行合一」を説く陽明学にも深く通じていました。この二つの学問を融合させた独自の思想は、学問仲間から尊敬を込めて「陽朱陰王(ようしゅいんおう)」と称されました。彼の門下生は、生涯で3000人にも上ると言われています。その中には、佐久間象山、山田方谷、渡辺崋山(わたなべ かざん)、横井小楠(よこい しょうなん)など、幕末から明治維新にかけて、新しい日本を創っていくことになる多くの俊英たちがいました。彼らは、一斎の教えを胸に、それぞれの立場で日本の近代化に貢献しました。
幕末のバイブル『言志四録』
一斎の思想を後世に伝える最大の功績が、42歳から晩年までの40年間にわたって書き綴った随想録『言志四録(げんししろく)』です。これは、『言志録』『言志後録』『言志晩録』『言志耋録』の全4巻、1133条からなる修養処世の心得を記したものです。この書物は、幕末の武士たちの間で、非常時の覚悟を示す書として愛読されました。特に、明治維新の立役者である西郷隆盛は、この『言志四録』の中から101条を選び、『南洲手抄言志録(なんしゅうしゅしょうげんしろく)』として座右に置き、生涯にわたる行動指針としました。一斎の言葉は、現代の政治家や経営者にも影響を与え続けています。小泉純一郎元首相が「三学戒」を引用して生涯学習の重要性を説き、野田佳彦元首相が「春風を以て人に接し 秋霜を以て自ら粛む」という言葉で政治家の心構えを示したように、その教えは時代を超えて生き続けています。
時代との葛藤と外交への貢献
一斎は、幕府の儒官として、当時の政治の最前線にも関わりました。83歳になった1854年(安政元年)、日米和親条約の締結に際しては、大学頭・林復斎(はやし ふくさい)を助け、外交文書の作成に尽力しました。しかし、彼の思想は、必ずしも当時の幕府の政策と一致したわけではありませんでした。門下生の渡辺崋山が「蛮社の獄」で無実の罪に問われた際には、一斎は彼を擁護する毅然とした態度を取らなかったため、後世、その「言行不一致」を批判されることもありました。一斎が亡くなったのは、1859年(安政6年)。安政の大獄で世の中が揺れ動く激動の最中であり、彼が亡くなったわずか9年後に、明治維新という新たな時代が訪れました。
佐藤一斎が登場する作品
佐藤一斎の生涯や思想は、彼の著作を通じて、また、彼を慕った弟子たちの伝記に登場する形で、現代に伝えられています。
- 小説:

- 書籍:
- 『言志四録』(佐藤一斎):彼の思想のすべてが詰まった随想録です。
- 『西郷南洲遺訓 附 手抄言志録及遺文』(山田済斎編):西郷隆盛が抜粋した『言志四録』が収録されています。
- 『代表的日本人』(内村鑑三):一斎の門下生である西郷隆盛の伝記の中で、彼の教えが言及されています。
- テレビ番組:
- 『言志四録の教え』(NHK):彼の思想を現代の視点で解説する番組が放送されました。
佐藤一斎ゆかりの地:岩村藩から江戸へ
佐藤一斎の足跡は、彼の生まれ故郷である岐阜県恵那市岩村町から、学問の道に生きた江戸へと繋がっています。
- 岩村歴史資料館(岐阜県恵那市岩村町):佐藤一斎をはじめ、岩村藩ゆかりの偉人たちの資料を展示しています。
- 佐藤一斎顕彰碑、座像(岐阜県恵那市岩村町):岩村町内には、一斎の功績を称える碑や像が建てられています。
- 深廣寺(じんこうじ)(東京都港区六本木):一斎の墓所がある寺です。
- 岩村の城下町: 200枚もの木板に一斎の名言が書かれており、家々の軒下に掲げられています。
佐藤一斎の遺産:現代社会へのメッセージ
佐藤一斎の生涯は、私たちに「生涯にわたる学びの重要性」を教えてくれます。彼の「三学戒」は、年齢や立場に関わらず、学び続けることの価値を力強く説いています。彼の『言志四録』は、単なる道徳の書ではありません。それは、私たちがどのように生きるべきか、どのように世の中と向き合うべきかという、人生の根本的な問いに対する答えを与えてくれます。西郷隆盛が終生の愛読書としたように、リーダーシップを志す者にとって、困難な時代を乗り越えるための羅針盤となるでしょう。一斎の物語は、一人の儒学者が、その思想と教えを通じて、時代を動かす指導者たちを育て、日本の未来を形作ることができることを証明しています。彼の言葉と精神は、現代に生きる私たちにも、学びと実践の大切さを問いかけ続けているのです。
(C)【歴史キング】
関連する書籍のご紹介

佐藤一斎一日一言 / 渡邉 五郎三郎 (監修)
単行本(ソフトカバー) – 2007/6/15

江戸時代の儒学者・佐藤一斎が後半生の40余年をかけて書き上げた『言志録』 『言志後録』 『言志晩録』 『言志?録』
この4つの語録集の総称が『言志四録』である。
全部で1133条ある条文の内容は、人間の生き方、豊かな人生を送るための心構え、政治法律、学問修養、倫理道徳など、まさに多種多様。
本書は古典活学における練達の士が、その中から366を厳選し、「一日一言」としてまとめたもの。
一斎は、門弟3000人を数える、いわば「人材育成のプロ」。
西郷隆盛も座右の書として愛読したという金言の数々は、現代でも、日常生活の実践や仕事の中で必ず役に立つだろう。
新書判ハンドブックで気軽に持ち歩ける好評「一日一言」シリーズ4作目。