
宮城県の偉人:志賀潔 — 赤痢菌を発見し、近代医学の夜明けを告げた研究者
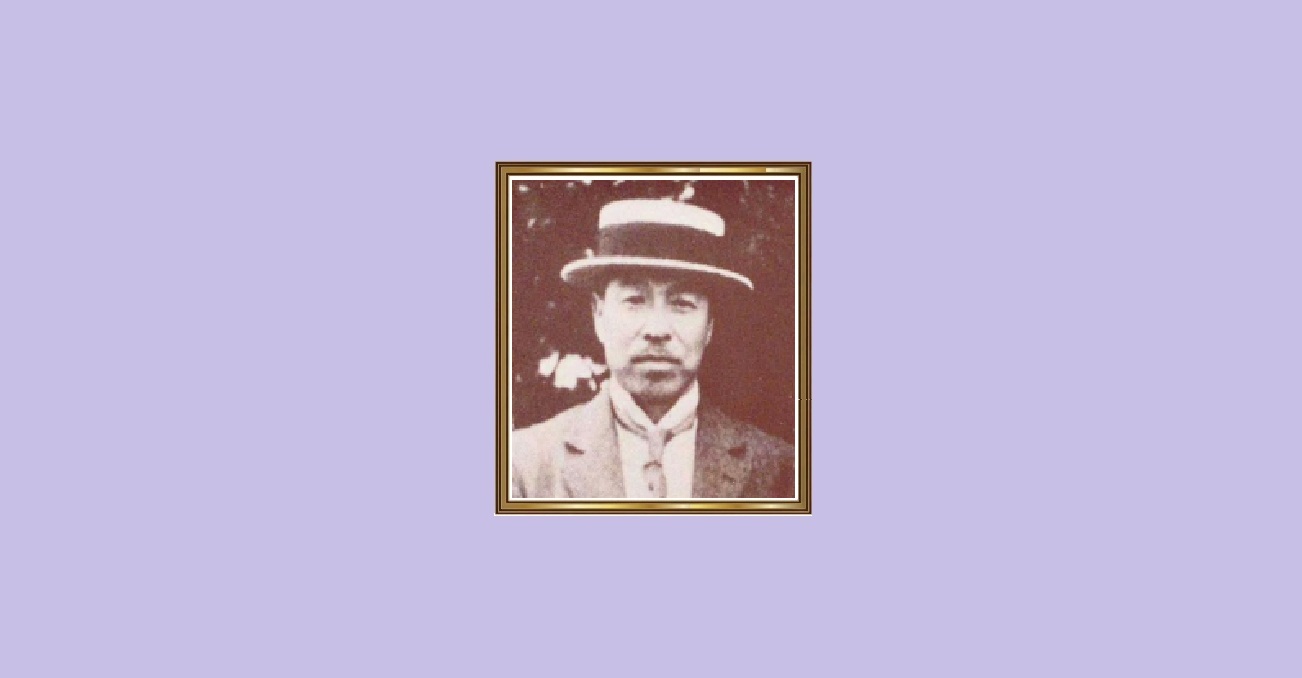

宮城県
「自ら信ずるところ篤ければ、成果自ら到る」
この言葉は、赤痢菌の発見者として世界に名を轟かせた医学者、志賀潔(しが きよし)がその生涯をかけて体現した信念です。明治3年(1871年)、宮城県仙台市に生まれた彼は、北里柴三郎やパウル・エールリッヒといった医学界の巨星に師事し、日本の近代化の中で世界に通用する科学研究の成果を成し遂げた先駆者です。彼の名を冠した「Shigella」(志賀菌)という学名は、主要な病原細菌に日本人の名前が冠された唯一の例となりました。
幼少期の苦難から医学の道へ
志賀潔は1871年(明治3年)、仙台藩士の佐藤信の四男として、陸前国宮城郡仙台(現在の仙台市)に生まれました。幼名は直吉。しかし、7歳の時に母の実家である志賀家の養子となり、名を「潔」と改めます。志賀家は代々仙台藩の藩医を務める家柄であり、彼は幼い頃から医学に触れる機会に恵まれました。育才小学校、宮城中学を経て、第一高等中学校(後の第一高等学校)に入学。東京での学生生活の中で、彼は北里柴三郎の門下生である青山胤通(あおやま たねみち)の講演を聴き、細菌学という新しい学問に強い関心を抱きます。1892年(明治25年)、帝国大学医科大学(現在の東京大学医学部)に入学。ここで、彼は「病気の原因を突き止め、予防法を見つけることこそが医者の使命である」という信念を固め、予防医学の道を志すようになります。
北里柴三郎との出会いと「赤痢菌」の発見
1896年(明治29年)、志賀は大学を卒業すると、福澤諭吉らの支援で設立された大日本私立衛生会伝染病研究所に入所。ここで、破傷風菌の純粋培養に成功し、世界的名声を得ていた北里柴三郎に師事します。当時、日本を初め世界各国では、原因不明の感染症である赤痢が猛威をふるっていました。伝染病研究所に入りたての志賀に、北里は赤痢の病原体究明という難題を託します。志賀は、研究室に寝床を作り、不眠不休で研究に没頭しました。患者から集まる検体をすべて培養、分離、染色、検鏡するという地道な作業を繰り返しました。半年におよぶ研究の末、彼は、ある特定の細菌が赤痢患者の血清とのみ特異的に反応することを発見。そして、1897年(明治30年)、ついに赤痢の病原菌である「赤痢菌」を発見しました。この偉業は、27歳という若さで成し遂げられたもので、世界の医学界に大きな衝撃を与えました。赤痢菌の学名「Shigella」は、志賀の名前が由来であり、病原細菌の学名に日本人の名前が冠された、ほとんど唯一の例となりました。
ドイツ留学と「化学療法」への貢献
赤痢菌の発見後、志賀はドイツへ留学し、フランクフルトの実験治療研究所で、「化学療法」の父と呼ばれるパウル・エールリッヒに師事します。エールリッヒは、「病原体にのみ特異的に作用する物質を合成化学的に創出する」という、画期的な研究に着手しようとしていました。志賀は、その助手に抜擢され、毎日何百というマウスの尾から血液を採取し、500種類以上ものアニリン色素誘導体を試すという、気の遠くなるような実験を繰り返しました。そして、1年半の歳月を経て、ついに最初の有効薬「トリパンロート」を発見。これは、アフリカの睡眠病の治療に有効であることが証明され、化学療法の最初の報告として注目されました。エールリッヒは、この功績を志賀との共著論文として発表し、志賀の謙虚で粘り強い姿勢を高く評価しました。
挫折と朝鮮での活躍
1914年(大正3年)、北里柴三郎が所長を務めていた国立伝染病研究所が、北里に相談なく文部省に移管されるという事件が起こります。これに猛反発した北里は、研究所を辞職。志賀も北里と共に辞職し、翌年、北里が私財を投じて設立した北里研究所の第一部長に就任しました。しかし、1920年(大正9年)、彼は、朝鮮総督府医院長・京城医学専門学校長として朝鮮へ渡ります。ここで、彼は医学教育と医事行政に深く関わり、1926年(大正15年)には、新たに創立された京城帝国大学の医学部長に就任。さらに1929年(昭和4年)には、同大学の総長にまで上り詰めます。
晩年の清貧と後世への遺産
志賀潔は、数々の名誉を得ながらも、清貧を貫いた人生を送りました。1945年(昭和20年)、東京大空襲で自宅と家財をすべて失うと、故郷の宮城県亘理郡坂元村磯浜の別荘「貴洋翠荘(きようすいそう)」に移り住み、そこで穏やかな余生を過ごしました。彼の別荘は、眼下に広がる大海原を眺めながら読書や執筆に耽る、彼にとっての理想郷でした。しかし、この磯浜の地でも、妻や長男、三男を相次いで亡くすという悲劇に見舞われます。1957年(昭和32年)、志賀は86歳で永眠しました。死後、仙台市により市民葬が行われ、その功績を称えられました。彼の墓所は、仙台市青葉区北山の輪王寺にあります。
志賀潔ゆかりの地:東北の足跡を辿る旅
志賀潔の足跡は、彼の故郷である仙台から、晩年を過ごした宮城県山元町、そして彼が学んだ東京へと繋がっています。
- 志賀潔銅像(仙台市青葉区勾当台公園):彼の功績を称える銅像が建っています。
- 山元町歴史民俗資料館(宮城県亘理郡山元町):志賀潔が晩年を過ごした別荘「貴洋翠荘」の資料を保管・展示しています。
- 志賀潔墓所(仙台市青葉区輪王寺):彼の遺骨が眠る墓所です。
- 東京大学医科学研究所(東京都港区):北里柴三郎のもとで、赤痢菌を発見した伝染病研究所の跡地です。
志賀潔の遺産:現代社会へのメッセージ
志賀潔の生涯は、私たちに「探求心と謙虚な姿勢」の重要性を教えてくれます。彼は、赤痢という社会問題の解決に、生涯をかけて取り組み、世界的な成果を成し遂げました。彼の「自ら信ずるところ篤ければ、成果自ら到る」という言葉は、現代社会が直面する様々な課題を解決するためには、目先の利益に惑わされず、自らの信念を貫くことの大切さを教えてくれます。また、彼の謙虚な人柄と清貧を貫いた姿勢は、名誉や財産ではなく、学問や社会貢献にこそ人生の価値があることを示しています。志賀潔の物語は、一人の研究者が、その探求心と情熱によって、社会全体をより良い方向へと導くことができることを証明しているのです。






