
京都府の偉人:角倉了以 — 嵐山に千光寺を建立し、高瀬川を拓いた水運の父
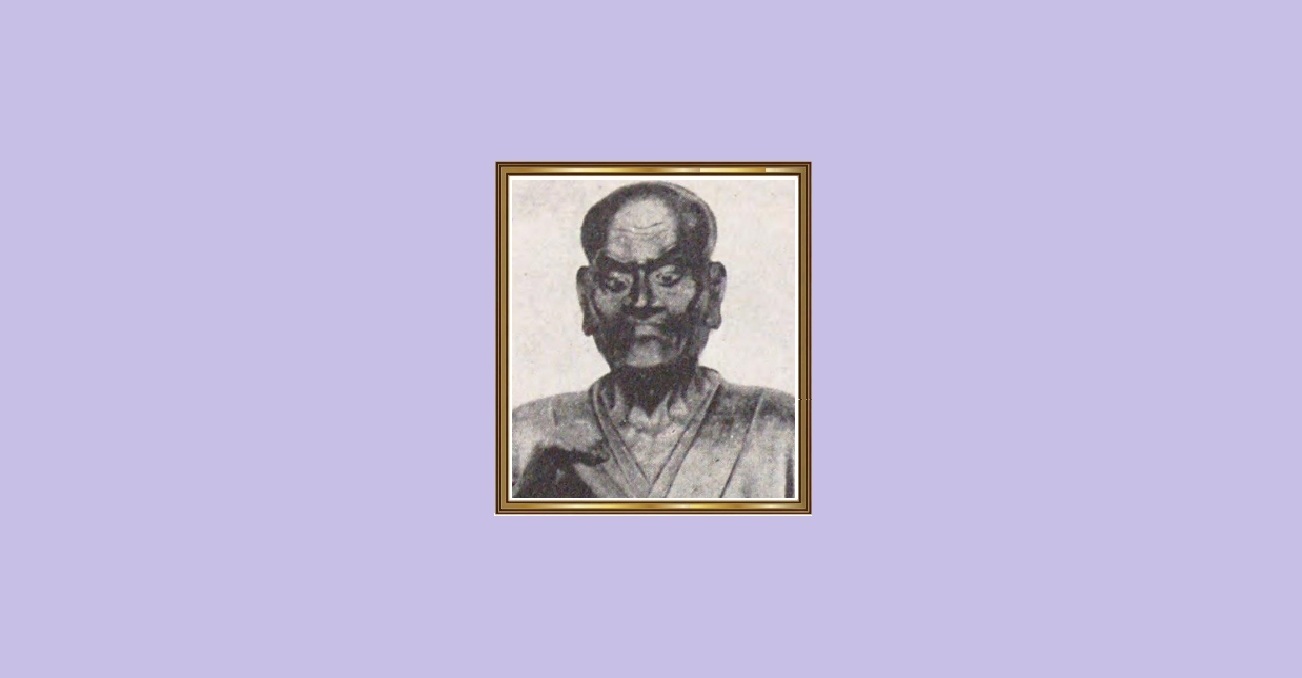

京都府
「ただ、事物の自らのまにまに備わりたる理(ことわり)を信じ、疑うことなし」
この言葉は、江戸時代初期に京都の豪商として、朱印船貿易と河川開削事業という、二つの壮大な事業を成し遂げた角倉了以(すみのくら りょうい)の揺るぎない信念を表しています。京都の嵯峨で金融業を営む家に生まれた彼は、海外貿易で得た莫大な富を元手に、国内では河川疏通事業に私財を投じ、京都と伏見を結ぶ人工運河「高瀬川」を開削しました。その先見性と事業家精神は、徳川の時代に衰退が危惧された京都を、再び繁栄へと導く礎を築きました。
医家から事業家へ:海と川のビジネスに挑む
角倉了以は、1554年(天文23年)、京都の嵯峨で代々医者であり、金融業(土倉)も営む吉田家の長男として生まれました。彼の祖父、吉田宗忠は、金融業で巨万の富を築き、父・吉田宗桂(そうけい)は、医者として天龍寺の長老に随行して明国へ渡るという、貴重な経験を持っていました。了以は、祖父から受け継いだ事業家精神と、父から受け継いだ科学的探究心を胸に、医業ではなく、新たな事業の道へと進むことを決意します。彼は、徳川家康から朱印状を得て、安南国(現在のベトナム)との朱印船貿易(角倉船)を開始します。この海外貿易で得た莫大な富は、彼の名を「京の三長者」の一人として知らしめるとともに、国内での壮大な事業の原資となりました。
河川開削事業への挑戦
海外貿易で成功を収めていた了以でしたが、彼は一時的な利益で終わる半博打的な事業に満足することはありませんでした。子々孫々まで続く安定した収益源を求めて、彼が目をつけたのが、生まれ育った京都の河川でした。1608年(慶長13年)、了以は幕府の許可を得て、大堰川(おおいがわ)(保津川)の開削に着手します。保津峡という巨岩が連なる難所を、火薬を使って岩を砕くなど、当時の最先端の土木技術を駆使して、わずか5ヶ月という驚異的なスピードで航路を完成させました。この成功は、丹波地方の豊富な物産や木材を京都へ運ぶことを可能にし、京都と丹波の双方に大きな利益をもたらしました。この偉業は幕府をも驚かせ、富士川や天竜川の開削も依頼されることになります。
京都の命運をかけた「高瀬川」開削
徳川家康が江戸幕府を開き、政治の中心が江戸に移ったことで、京都の衰退が危惧されていました。この状況を憂慮した了以が、京都の繁栄のために着手したのが、鴨川と並行する人工運河「高瀬川」の開削です。
- 高瀬川開削の目的: 鴨川は、満水時と渇水時の水位の差が激しく、安定した水運には不向きでした。了以は、水深が一定に保たれ、安定的な水量が流れる運河を掘ることで、京都と伏見、そして淀川を経て大坂へと続く、物流の大動脈を築こうと考えました。
- 莫大な私財の投入: 高瀬川の開削費用は、現代の価値に換算して約150億円という莫大なものでしたが、了以はこれを私財で賄いました。さらに、曳き子(ひきこ)と呼ばれる人足が綱で舟を引く、平底の「高瀬舟」を建造するなど、インフラの整備から運営までを一貫して行いました。
- 慈悲深い事業家: 高瀬川の開削工事中、三条河原で処刑された豊臣秀次と妻子の一族を埋めた「悪逆塚」が荒れ果てているのを見つけた了以は、豊臣家の一族を弔うために「瑞泉寺(ずいせんじ)」を建立しました。これは、彼の慈悲深い人柄を物語るエピソードです。
こうして高瀬川は、1614年(慶長19年)、了以が亡くなる年に竣工しました。これにより、京都は伏見港を通じて全国と繋がる物流の拠点となり、政治都市としての地位は失っても、経済・文化の中心地としての繁栄を維持することができました。
「無冠の大使」と後世への遺産
了以は、高瀬川が完成した年に60歳で亡くなりました。しかし、彼の事業は、息子の素庵(そあん)へと引き継がれ、高瀬川の通行料収入は、明治時代まで角倉家に莫大な富をもたらしました。彼の事業家精神は、現代の視点から見ても非常に先進的です。国内での河川開削と海外貿易という、高リスク・高リターンの事業を両立させ、その利益を長期安定的な収益が見込める社会資本整備に投資するという手法は、今日のベンチャービジネスやインフラ事業の原型ともいえるでしょう。また、彼の慈悲深い人柄は、保津川開削工事で命を落とした人足を弔うために「大悲閣千光寺(だいひかくせんこうじ)」を建立したことからもわかります。これは、彼の事業が単なる金儲けのためではなく、人々の生活を豊かにし、社会に貢献するという、強い理念に基づいていたことを示しています。
角倉了以ゆかりの地:水運の足跡を辿る旅
角倉了以の足跡は、彼の故郷である嵯峨から、高瀬川開削の拠点、そして彼の信仰の地へと繋がっています。
- 角倉了以邸跡(京都市中京区木屋町通二条下る西側):高瀬川の開削を監視するため、高瀬川に面した場所に屋敷を構えていました。現在は日本銀行京都支店の敷地となっており、石標がその跡を示しています。
- 角倉了以別邸跡(中京区木屋町通二条下る東側):現在の飲食店「がんこ高瀬川二条苑」の場所です。
- 角倉了以水利紀功碑(京都市伏見区三栖半町・伏見みなと公園):高瀬川開削の功績を称える顕彰碑です。
- 高瀬川一之船入(いちのふないり)(京都市中京区木屋町通二条下る上樵木町):高瀬川を運行する舟の荷物の揚げ降ろしをする船溜りで、現在は史跡として石標が建ちは高瀬川一之船入の跡を示している。
- 大悲閣千光寺(京都市西京区嵐山中尾下町62):保津川の開削で命を落とした人足を弔うため、了以が建立した寺です。
- 瑞泉寺(京都市中京区木屋町通三条下ル石屋町114):豊臣秀次とその一族を弔うため、了以が建立した寺です。本堂に了以と長男の角倉素庵(角倉保庵の説あり)の像が安置されている。
- 常寂光寺(京都市右京区嵯峨小倉山小倉町3):境内には、保津川の舟運に使われた高瀬舟が展示されています。
- 花のいえ(角倉了以邸址)庭園(京都府京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町9):嵐山・渡月橋からすぐ。京都の豪商・角倉了以の邸跡に開かれた旅館に残る、大名茶人・小堀遠州作庭と伝わる庭園。
- 角倉了以墓所(京都市右京区嵯峨二尊院):了以と息子・素庵が眠る墓所です。
角倉了以の遺産:現代社会へのメッセージ
角倉了以の生涯は、私たちに「先見性と行動力、そして人間愛」の重要性を教えてくれます。彼は、海外で得た成功を国内の社会基盤整備に活かし、私利私欲だけでなく、社会全体の繁栄を見据えた事業を行いました。彼の河川開削事業は、単なる土木工事ではありませんでした。それは、物流を改善し、経済を活性化させ、人々の暮らしを豊かにするという、明確なビジョンに基づいたものでした。角倉了以の物語は、一人の商人が、その知恵と財力、そして慈悲深い心によって、時代の流れを読み、国の未来を形作ることができることを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、ビジネスの力で社会をより良くしていくことの可能性と、真のリーダーシップとは何かを問いかけ続けているのです。






