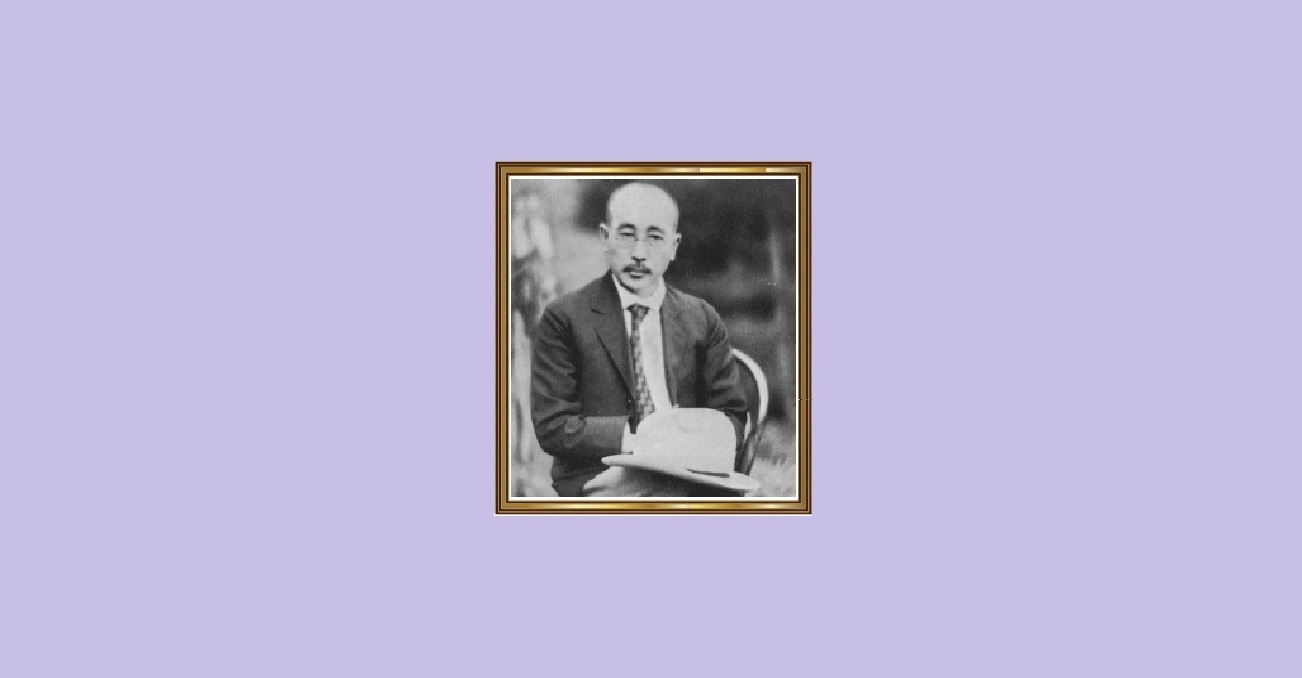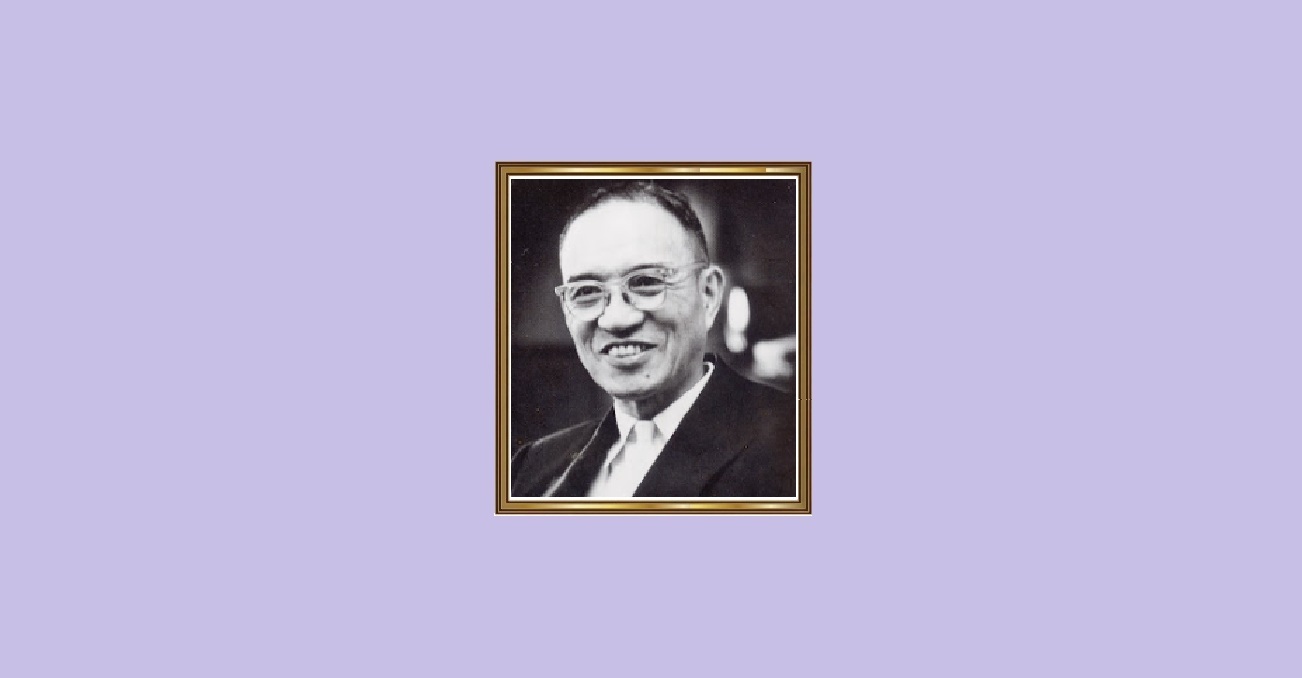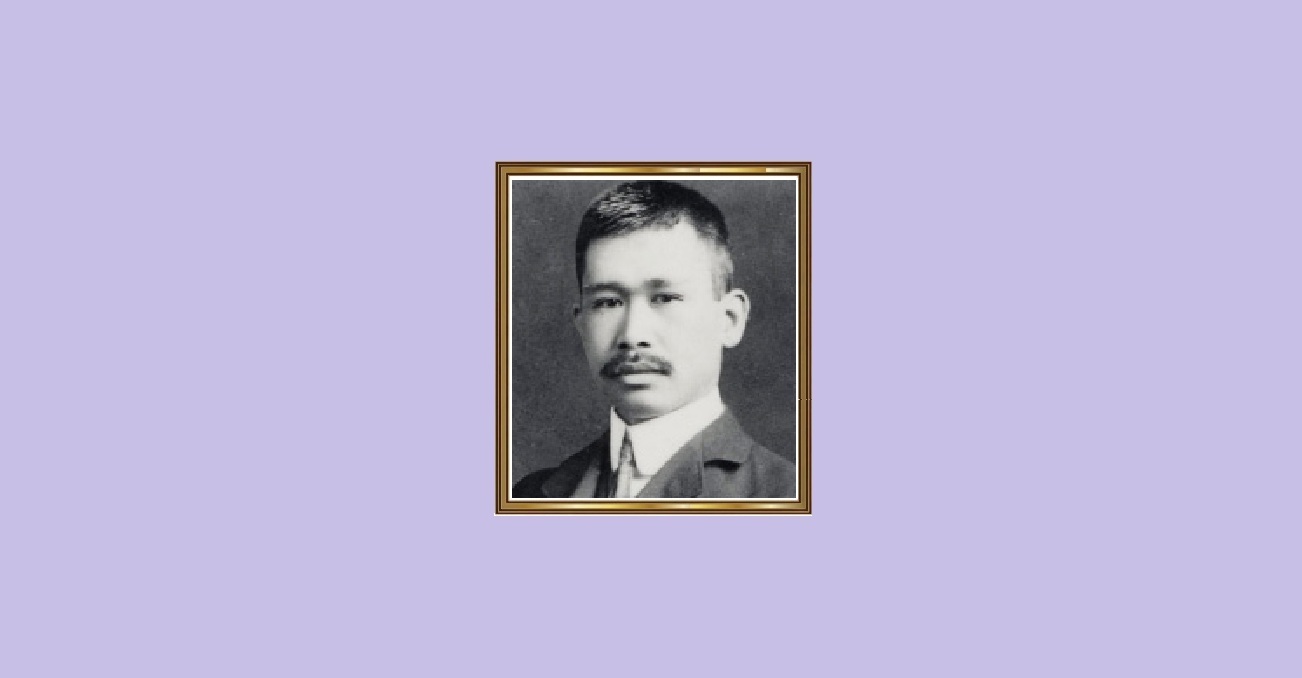徳島県の偉人:東洲斎写楽 — 10ヶ月で消えた「謎の絵師」が残した不朽のリアリズム

「写楽は阿波藩の能役者、斎藤十郎兵衛である」
この記述は、約10か月の短い期間に140点余りの個性的で強烈な役者絵を世に送り出し、忽然と姿を消した東洲斎写楽(とうしゅうさい しゃらく)の正体に迫る、江戸時代の文献『増補浮世絵類考』に残されています。
生没年不詳、その出自も謎に包まれた写楽ですが、その作品が日本の美術史、そして世界の肖像画史に与えた衝撃は計り知れません。本稿では、写楽の正体とされる阿波国(現在の徳島県)の能役者・斎藤十郎兵衛説を中心に、写楽がなぜ当時の浮世絵界の常識を破壊し、いかにして世界的な評価を獲得したのか、その謎と功績を深掘りします。
彗星の如く現れた謎:無名の絵師の衝撃的デビュー
写楽の活動期間は、寛政6年(1794年)5月から翌7年(1795年)1月までの、わずか10か月間に限定されています。しかし、この短い間に彼は145点以上もの作品を版行しました。
蔦屋重三郎の勝負と「黒雲母摺り」
写楽が浮世絵界に登場した背景には、当時の江戸のヒットメーカーであり、出版プロデューサーであった版元・蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)の存在があります。蔦重は、老中・松平定信による「寛政の改革」の引き締め策で、芝居の興行が低迷し、新しい振興策が求められていた時期に、無名の新人である写楽を大々的に売り出しました。デビュー作は、背景にキラキラと光る鉱物(雲母)の粉末を混ぜた絵の具を用いる豪華な「黒雲母摺り(くろきらずり)」の大判役者大首絵28図。これは、当時の浮世絵界の常識を覆す、破格のデビューでした。
観客が戸惑った「超リアル」な描写
写楽の作品が従来の役者絵と一線を画していたのは、その異常なほどの写実性と大胆なデフォルメにあります。当時の役者絵は、ファンのためのブロマイド的な役割が強く、役者を美化したり、役柄の設定に忠実に描いたりするのが通例でした。しかし、写楽は容姿の欠点(目の皺、鷲鼻、受け口など)を隠すことなく強調し、その役者自身の個性や内面を巧みに描き出しました。特に「三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛」や「市川蝦蔵の竹村定之進」といった代表作は、芝居の一瞬の緊張感や、役者の迫真の表情を見事に捉えています。この前代未聞のリアルな描写は、当時の人々には賛否両論でした。贔屓の役者を美しく見たいファンからは「あまりに真を画(えが)かんとて、あらぬさまにかきなせしかば、長く世に行われず」と酷評され、写楽の作品は商業的には成功しなかったとされています。これが、彼が短期間で姿を消した最大の理由とされています。
謎の正体:能役者「斎藤十郎兵衛」説の浮上
写楽が忽然と姿を消したことで、彼の正体をめぐっては、浮世絵史上最大のミステリーが生まれました。【江戸時代の唯一の記録】写楽の正体に言及した唯一の江戸時代の記録は、考証家・斎藤月岑(さいとう げっしん)が記した『増補浮世絵類考』の記述です。
「俗称斎藤十郎兵衛、八丁堀に住す。阿州侯の能役者也。」
この記述は長らく、写楽の正体を知る手掛かりとなりましたが、能役者にこれほどの絵の才能があるとは考えづらく、「写楽別人説」が主流となっていました。初代歌川豊国、喜多川歌麿、葛飾北斎、果ては版元の蔦屋重三郎本人など、実に多くの人物が写楽の候補として挙げられました。
近年の研究による実在の裏付け
しかし、平成時代に入り、写楽=斎藤十郎兵衛説を裏付ける決定的な資料が発見されます。
- 実在の証明: 能役者の公式名簿や阿波藩の古文書から、斎藤十郎兵衛という人物が実在し、阿波徳島藩主・蜂須賀家お抱えの能役者であったことが確認されました。
- 居住地の特定: 江戸の文化人録『諸家人名江戸方角分』の八丁堀の項目に「号写楽斎 地蔵橋」の記録があり、八丁堀に住んでいた能役者という条件が一致しました。
- 過去帳の発見: 埼玉県越谷市の寺院の過去帳から、斎藤十郎兵衛が文政3年(1820年)に死去したという記録が発見され、八丁堀地蔵橋に住んでいた能役者が実在したことが裏付けられました。
これらの実証的な研究の結果、写楽の正体は、阿波藩の能役者・斎藤十郎兵衛であったという説が、現在最も有力となっています。舞台の裏側を知る能役者であったからこそ、役者の素顔や演技の本質を捉えた、あの強烈な役者絵が描けたのではないか、という解釈も有力です。
世界的な再評価:「世界三大肖像画家」の伝説
写楽の作品は、江戸時代には人気を得られず姿を消しましたが、その真価は、時代を超えて西洋の美術界で再発見されました。
ドイツ人心理学者の衝撃
1910年(明治43年)、ドイツの美術研究家ユリウス・クルトが研究書『SHARAKU』を刊行しました。クルトは、当時の歌舞伎の背景を知らない視点から、写楽の作品を、役者の内面を映し出した肖像画の傑作として絶賛しました。このクルトの著作がきっかけとなり、写楽は世界的な知名度を獲得し、日本国内でもその評価が逆輸入される形で高まっていきました。
「三大肖像画家」論の真実
写楽の評価を語る際、「写楽はレンブラントやベラスケスと並ぶ世界三大肖像画家の一人である」という言葉がしばしば引用されます。しかし、クルトの原著には、この「三大肖像画家」という言葉や、レンブラント、ベラスケスといった固有名詞は一切記載されていません。この誤解は、日本の浮世絵研究家が、写楽をレンブラントらに比肩する存在として紹介した文章が、いつしか「クルトの言説」として一人歩きしてしまったことによるものです。この事実は、写楽の評価が、彼の卓越した画力だけでなく、謎めいた存在として世界的な関心を集める中で、誇張された側面も持っていることを示しています。
📍東洲斎写楽ゆかりの地:謎の巨匠の足跡を辿る旅
写楽の足跡は、彼の正体とされる能役者・斎藤十郎兵衛の故郷である徳島から、作品を発表した江戸の地へと繋がっています。
- 東光寺(徳島県徳島市寺町):斎藤十郎兵衛の戒名が記されているお墓があることから、写楽の墓所とされるが、真相不明。
- 法光寺(埼玉県越谷市三野宮1336):平成9年(1997年)に斎藤十郎兵衛の過去帳が発見されたことで写楽のお墓説の脚光を浴びた。
- 斎藤十郎兵衛居住地跡(東京都中央区日本橋茅場町3丁目付近):やきとり宮川、雑貨の「赤札屋」が目標、赤札屋の南隣の細い道を左折した所にあたるが、説明版も碑も全くなし。
💬東洲斎写楽の遺産:現代社会へのメッセージ
東洲斎写楽の生涯は、私たちに「真の独創性と革新の価値」を教えてくれます。
彼は、当時の世間に受け入れられず、わずか10か月で姿を消しましたが、その作品は200年の時を超えて、世界的な評価を獲得しました。彼の作品が今なお私たちを惹きつけるのは、単なる技術の高さだけでなく、人間の内面や本質を、美醜を問わず捉えようとした、その徹底したリアリズムにあります。
彼は、観客の期待する「アイドル像」ではなく、舞台上で演じる「一人の人間」を描きました。写楽の物語は、一時の流行に流されず、自らの信じる表現を貫くことの尊さを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、自己の表現に誠実に向き合い、真に価値あるものは時代を超えて評価されるという、揺るぎない確信を、力強く語りかけているのです。

2025大河ドラマ{べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜}では、東洲斎写楽=斎藤十郎兵衛説は採用されず、喜多川歌麿が描き、蔦屋がとりまとめた、クリエイターたちの合作である【蔦屋工房説】が用いられました。まぁ、そもそも、東洲斎写楽=斎藤十郎兵衛で確定!ってわけではなく、『その説が濃厚!』って話であるので、これもまた面白い話でした☺