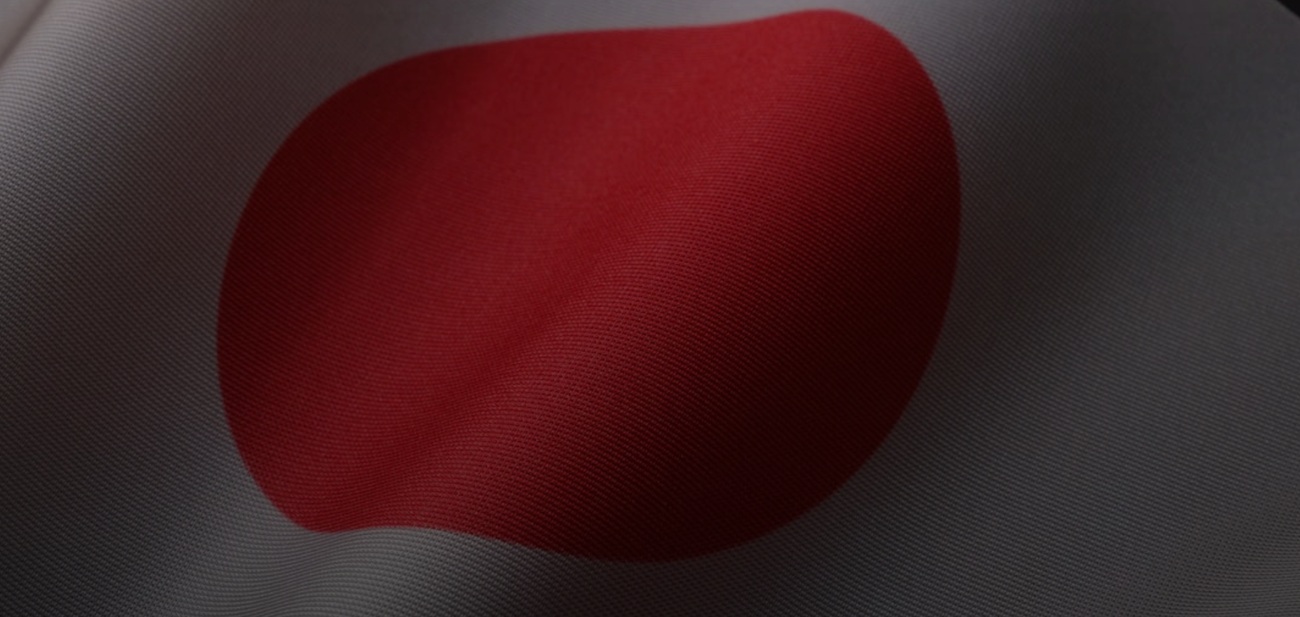第23回 GHQとメディア統制――日本人の記憶は誰が作ったのか?

23-1. プレスコードと検閲の実態
「民主主義」の影に隠された言論統制
1945年(昭和20年)8月15日、日本がポツダム宣言を受諾し、GHQ(連合国軍総司令部)による占領が開始されると、日本社会のあらゆる分野で「民主化」が推進されました。しかし、その「民主主義」という名の改革の影で、GHQは徹底的な言論統制を行っていました。それが「プレスコード」と呼ばれる検閲制度です。このプレスコードは、日本のメディアを通じて国民に「自虐史観」を植え付け、戦後の日本人の「記憶」と「常識」を作り上げる上で決定的な役割を果たしました。
プレスコードの導入とその目的
GHQは、占領開始直後の1945年9月10日に「日本新聞遵守事項」を、9月22日には「プレスコード」を、さらに10月8日には「ラジオ放送遵守事項」を次々と発令し、日本の新聞、出版、ラジオ放送など、あらゆるメディアに対する検閲を導入しました。その目的は、単に軍事情報を統制するだけでなく、日本の戦前・戦中の「軍国主義」や「超国家主義」を徹底的に排除し、民主主義と平和主義の思想を国民に浸透させることにありました。
しかし、その実態は、GHQが自らの占領政策を円滑に進めるための「情報操作」であり、日本国民の「思想改造」でもありました。プレスコードによって検閲される対象は、広範囲にわたり、GHQに都合の悪い情報は徹底的に排除されました。
「検閲方針30項目」に見る思想統制
GHQの検閲方針は、特にその「検閲方針30項目」によって明確に示されています。これには、以下のような内容が含まれていました。
- GHQ批判の禁止: 連合国軍やGHQ、占領政策に対する批判的な報道は一切禁止されました。これは、GHQの絶対的な権威を確立し、占領政策への異論を封じるためのものでした。
- 東京裁判批判の禁止: 東京裁判の正当性や公平性に対する批判は、厳しく取り締まられました。これは、東京裁判が日本の戦争責任を断罪し、「自虐史観」を国民に植え付けるための重要なツールであったためです。パール判事の意見書など、東京裁判の不当性を訴える意見は、国民の目に触れることがありませんでした。
- 天皇制批判の禁止、および擁護の禁止: 天皇制を批判する報道は禁止された一方で、天皇の神格化や美化、天皇を擁護する論調も禁止されました。これは、天皇の政治的権力を奪い、民主主義の象徴としての天皇像を確立するためのものでしたが、結果的に天皇の「戦争責任」をめぐる議論をタブー視する空気を作り出しました。
- 大東亜戦争肯定の禁止: 大東亜戦争を「侵略戦争」以外の目的で評価する言論は、一切許されませんでした。日本の「生存権」をめぐる苦悩や、アジア諸国の「白人支配からの解放」という側面など、日本の大義名分については、徹底的に隠蔽されました。
- 原爆投下批判の禁止: 広島・長崎への原子爆弾投下や、日本各地への無差別爆撃に対する批判的な報道は禁止されました。これにより、日本は「被害者」としてではなく、「加害者」としての側面のみが強調され、戦勝国の戦争行為については一切問われないという「ダブルスタンダード」が確立されました。
- 神道・軍国主義賛美の禁止: 神道や武士道、特攻精神など、戦前の日本の精神的支柱となった思想や文化は、「軍国主義」の温床として排除され、その賛美は禁止されました。
検閲の実態と「鉛筆なめなめ」の時代
プレスコードによる検閲は、日本の新聞社や出版社に設置されたGHQの検閲官によって行われました。彼らは、原稿や紙面を事前にチェックし、問題のある箇所を削除したり、書き換えを命じたりしました。日本の記者や編集者は、GHQの検閲官の意向を忖度し、自ら記事を修正する「自主規制」を行うようになりました。これを「鉛筆なめなめ」と揶揄されたりもしました。
当時の日本のマスコミは、GHQの意図を正確に把握し、検閲官から「ダメ出し」を食らわないように、自ら「戦勝国の正義」に沿った報道を率先して行うようになったのです。ダグラス・マッカーサー連合国最高司令官が1951年に米国議会で「大東亜戦争は自衛戦であった」と証言した際、日本のマスコミがそれをほとんど報じなかったのは、このメディア統制の「成果」と言えるでしょう。
日本人の「記憶」と「常識」の形成
このプレスコードと検閲は、日本の国民に「自虐史観」を深く植え付ける上で極めて効果的でした。GHQは、教育改革とメディア統制を一体として運用することで、日本人の心の中に「日本は悪い国だった」「過去の日本は間違いだらけだった」という罪悪感を徹底的に刷り込みました。これにより、日本人は自国の歴史や文化に誇りを持つことをためらい、自己否定の歴史観が戦後世代の「常識」として定着していったのです。
家族よりも個人の権利の方が大事だという価値観が刷り込まれて、家族がまるで抑圧装置のようにされてしまい、戦後の個人主義の導入が伝統的な家族観が破壊されたのです。また、自分の国を自分で守るという気概すら失い、日本の防衛意識の希薄化も、この占領下の言論統制と教育改革の延長線上にあるといえるでしょう。
「記憶のねじれ」を解きほぐすために
GHQによる占領はとっくに終わっています。にもかかわらず、いまだにその占領中にGHQが作った「日本国憲法」の解釈や、教科書に描かれた「日本像」が、私たちの歴史認識を強く規定しているという現状があります。これは、プレスコードと検閲が、単なる一過性の言論統制ではなく、日本人の「記憶」そのものを「ねじ曲げ」、その「常識」を「作り上げた」という事実を示しています。
私たちは、この「記憶のねじれ」を解きほぐし、自虐史観を克服する必要があります。そのためには、GHQのメディア統制の実態を深く理解し、何が隠蔽され、何が強調されたのかを客観的に検証することから始めるべきです。真の歴史認識は、光と影の両方を見つめ、複雑な歴史の真実を理解することでしか得られません。この真実の探求こそが、未来へとつながる真の日本人としての誇りを取り戻す第一歩となるでしょう。
23-2. 映画・出版・放送の“洗脳”政策
情報空間を支配し、日本人の意識を塗り替える
第二次世界大戦後、日本に降り立ったGHQ(連合国軍総司令部)は、日本の社会を根底から変革しようとしました。その目的は、単に軍隊を解体し、民主的な制度を導入するだけでなく、日本人自身の心の中にある「戦争の記憶」や「国家観」を根本から変えることにありました。GHQは、この目的を達成するために、映画、出版、そしてラジオ放送といったあらゆるメディアを巧みに利用し、まるで綿密に計画されたかのような“思想改造”政策を進めたのです。
メディアを通じて放たれた「罪の物語」
GHQは、占領初期に「プレスコード」と呼ばれる厳格な検閲制度を導入し、日本の言論空間を掌握しました。しかし、彼らの戦略は、単に情報の発信を制限するだけではありませんでした。GHQは、自らの意図する「新しい物語」を積極的に作り出し、それを日本のメディアを通じて国民に浸透させようとしました。この物語は、後の「自虐史観」の土台を築き上げることになります。
- 映画が描いた「新しい価値観」:映画は、当時の日本人にとって最も身近で影響力のある娯楽の一つでした。GHQは、日本の映画製作に対し、徹底的な統制を敷きました。戦前の軍国主義や天皇制を賛美する内容、日本の誇りを鼓舞するようなテーマは厳しく排除されました。その代わりに、民主主義の素晴らしさ、平和主義の重要性、そして日本の戦争責任を強調する映画の製作が奨励されました。特に、日本の伝統的な家族制度が「封建的」で個人の自由を抑圧するものとして描かれ、欧米型の個人主義が理想として提示されました。これにより、国民の意識は、かつて日本人が大切にしていた温かい家族の絆よりも、個人の権利や自由を尊重する方向へと誘導されていきました。映画は、日本人の心に「日本は悪かった」というメッセージを視覚的に、そして繰り返し植え付ける強力なツールとなったのです。
- 出版物が伝えた「書き換えられた歴史」:教科書だけでなく、一般の書籍や雑誌もGHQの厳重な検閲下に置かれました。戦前・戦中に書かれた多くの本が「不適当」とされ、出版が禁じられました。同時に、GHQの意図に沿った「新しい歴史観」に基づく出版物が推奨されました。東京裁判の判決内容を詳しく解説するものや、戦争の悲惨さ、日本の加害責任を強調する手記などが数多く世に出されました。これにより、東京裁判で定義された「平和に対する罪」や「人道に対する罪」といった概念が、まるで揺るぎない真実であるかのように国民の間に浸透していきました。マッカーサー連合国最高司令官が、後年、大東亜戦争を「自衛戦であった」と語った重要な証言ですら、当時の日本の主要なメディアがほとんど報じなかったのは、この出版統制と、メディア自身の自律的な検閲体制が確立されていた何よりの証拠と言えるでしょう。
- ラジオ放送が響かせた「一方的な声」:ラジオは、当時、最も広範な人々に直接情報を届けることができるメディアでした。GHQはNHK(日本放送協会)を厳しく監督し、ニュースや教育番組を通じて、直接的に「民主主義」や「平和主義」の思想を国民に伝えました。天皇が自らの神性を否定する「人間宣言」を行った際も、その内容はラジオを通じて全国津々浦々まで伝えられ、戦前の天皇の絶対的な存在感を打ち消す役割を果たしました。また、戦争の悲惨さを訴える番組や、戦犯の「罪」を糾弾する内容の番組も繰り返し放送され、日本人に「自らの過去は悪である」という認識を植え付けることに貢献しました。
「作られた罪悪感」と国民の精神的変容
GHQがこれらのメディアを通じて行った“洗脳”政策は、戦後日本の社会と文化に、計り知れないほど深い影響を残しました。この「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム」は、日本人の精神的基盤を揺るがし、二度と白人国家に逆らわない、従順な国民を作り出すという明確な狙いを持っていました。
「日本は悪い国だった」「過去の日本は間違いだらけだった」という自己否定の歴史観が徹底的に刷り込まれた結果、日本人から自国の歴史や文化に対する「プライド」が失われ、国家というものに対する意識すら希薄になっていきました。かつて日本人が持っていた、自らの国を自らの手で守るという気概までもが失われていったのです。
現在でも、日本の防衛や国家主権が脅かされた際に、国民が真剣に怒りを覚えない、あるいは関心を示さないという現状は、この占領下の言論統制と教育改革が残した「戦後の宿題」であると言えるでしょう。
「占領の終わり」と「記憶の再構築」
アメリカによる日本の占領は、すでに遠い過去の出来事です。しかし、驚くべきことに、その占領中にGHQが作り上げた「日本国憲法」の解釈や、教科書に描かれた「日本像」が、いまだに私たちの歴史認識を強く規定しているという現実があります。これは、GHQのメディア統制が、いかに巧妙で、かつ長期的な影響力を持っていたかを物語っています。
私たちは、この「占領の呪縛」から解放される必要があります。そのためには、GHQによるメディア統制の実態を深く理解し、何が隠蔽され、何が強調されたのかを客観的に検証することから始めるべきです。真の歴史認識は、光と影の両方を見つめ、複雑な歴史の真実を理解することでしか得られません。そして、その上に立って、日本人本来の心とプライドを取り戻し、自らの国を自らの手で守る気概を持つこと。これこそが、未来へとつながる「もう一つの昭和史」を語り継ぐための重要な課題なのです。
(C)【歴史キング】
関連する書籍のご紹介

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。